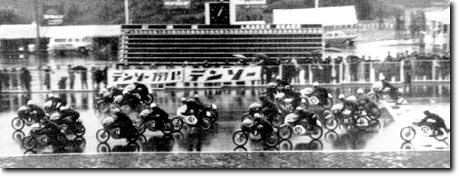|
|
 |
|
1954年のブラジル・サンパウロ市市制400年記念国際モーターサイクルレースへの出場によって具体的な前途を見出し、マン島TT出場の宣言に至ったHondaは、1959年のマン島TT初出場6位入賞、1960年の西ドイツGPにおける初表彰台獲得などを経て、ついに1961年緒戦スペインGPで記念すべき初優勝を達成した。続く第2戦では日本人ライダーによる優勝もなし遂げ、さらに最大の目標であったマン島TTも制覇。この1961年には念願の世界タイトル獲得も実現させている。
しかしその頃、Hondaはもうひとつの、否むしろさらに大きなプロジェクトを進行させていた。それは、日本国内に国際的なレーシングコースを完成させ、2輪4輪を問わずレースそのものを我が国に定着させるという、根元的なプロジェクトだった。
|
 |
 |
 |
本田宗一郎のイマジネーションは、いつも周囲の理解を超える先見性と拡がりを持っていた。当初は、本格的なテストコースの不備からその建設を論じられた専用レーシングコースだったが、宗一郎社長の目は遙か大きな未来と理想を見据えていたのだった。「ないモノは、自分で造ればいいじゃないか!」…その一言が社内に響いたのは1959年のことだったと伝えられている。マン島TT初挑戦から半年も経たずして、本田宗一郎は一気にモータースポーツへの情熱をほとばしらせていったのだ。 |
|
 |
| 1960年春、社内に「モータースポーツランド設立委員会」を発足させ、Hondaは国際レーシングコース建設に向けてその第一歩を記した。同年8月には、鈴鹿に建設地を決定。その年の暮れにはスタッフをヨーロッパに派遣し、各国のサーキット視察と設計者の人選を進めるという、まさに電光石火の進行ぶりである。考えてみれば、この1960年の時点でHondaはまだGPでの勝利を経験してはいない。そんな駆け出しのメーカーが国際レーシングコースの建設に乗り出すというのだから、話は破天荒である。 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
各種の準備や認可を終え、実際の現地測量と資材搬入が始まったのは1961年の7月。8月25日に地鎮祭をとりおこない、工事は一気に加速した。その頃Hondaチームは125と250で快進撃を続け、初のタイトル獲得が視野に入るところまで来ていた。コース建設は実際の工事に合わせて調整を続けながら、1962年1月15日に最終的なコースレイアウトが決定され、付帯設備、関連施設なども着々と形作られていった。また同時に職員教育、さらにはレース運営にまつわる諸規定の整備など、日本におけるレース運営がゼロの状態から準備されていった。 |
|
 |
| そして1962年9月20日、我が国初の国際レーシングコースが、ついに竣工式を迎えた。その年Hondaは125、250、350ccの3クラスでライダー/メーカーのタイトルを決定していたが、関係者はその喜びにひたる暇もなく「次の準備」を始めていたのだ。その年11月3〜4日に迫った第1回全日本選手権ロードレース大会は、鈴鹿における初の本格的な国際ロードレースであり、また翌1963年に開催を予定している世界選手権ロードレース日本グランプリのためのFIMの査察と国際トラックライセンス認可をとりつけるための重要なレースだったのだ。 |
 |
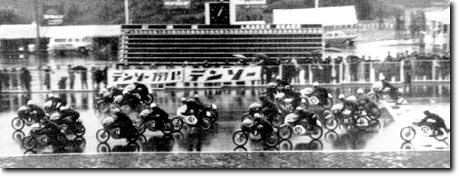 |
 |
| 1962年11日3日・土曜日、第1回全日本選手権ロードレース大会1日目。鈴鹿は大雨にみまわれたが、それでも我が国初の2輪ロードレースに約10万人もの大観衆が集まった。悪天候の中、観客はぬかるむ道に足を取られて四苦八苦したが、レースそのものは大きな問題もなくノービス50、250、セニア125、350の4クラスを開催した。そして翌4日・日曜日は好天に恵まれ、ノービス125、350、セニア50、250の4クラスのレースが開催され、実に17万人もの観客が鈴鹿サーキットを訪れたという。 |
 |
 |
 |
この日、セニア50のレースではスズキのエースライダーであるエルンスト・デグナーが4周目にヘアピン手前の右コーナーで転倒。以来ここはデグナーカーブと呼ばれるようになった。250ccクラスでは、世界タイトルを決定したジム・レッドマンがその素晴らしい走りを披露し、2位に20秒以上の差をつけて優勝。この時レッドマンが記録した2分36秒4のラップタイムが、鈴鹿サーキットにおける初のコースレコードとして記録された。 |
|
 |
|
 |
| こうして日本における初めてのロードレースは、大盛況、大成功の内にその幕を閉じ、翌1963年の日本グランプリ開催も決まった。しかし、その63年は、Hondaにとってこれまでにない苦戦と敗北を味わう厳しいシーズンとなっていた。50、125の軽量クラスでは、2ストロークエンジンで瞬く間に世界トップレベルとなったスズキが好調を見せ、常に表彰台の頂上を占める実力を発揮していた。350ccクラスではHondaが完全にMVアグスタを封じ込めたものの、250ccクラスでは単気筒モトモリーニを駆るタルキニオ・プロビーニが想像を越えた好走を見せ、レッドマンと一進一退の攻防を続けていた。 |
 |
 |
|
 |
|
1963年の最終戦となる日本GPを前にして、350ccクラスではレッドマンが最終戦を待たずしてタイトルを決めたものの、すでに50、125はスズキに栄冠がもたらされ、これで250を落とせば、Hondaにとって勝利数、タイトル数ともに1961年以来最悪の成績となることは明らかだった。その250ccクラスではレッドマン、プロビーニともに42ポイントの同点で、タイトル決定を最終戦鈴鹿に持ち越していた。
日本における初の世界GPは、そんな状況をはらみながら開催されるに至った。期日は1963年11月10日。それは、日本国中の悲願であった東京オリンピックの開催から丁度11ヶ月前の、昭和38年のことだった。
|
 |
 |
 |
レッドマン/Hondaとプロビーニ/モトモリーニは、好対照なライバルだった。Hondaチームの「キャプテン」と呼ばれたレッドマンは、決して天才的な煌めきのライディングを見せるライダーではなかったが、確実にポイントを稼ぐ安定感に満ちた正統派ライダーの筆頭にあげられる存在だった。一方プロビーニは、モンディアルやMVで世界タイトルの経験もあるイタリアを代表する熱血ライダー。特に単気筒モリーニを駆るようになってからは「火の玉男」と呼ばれるほど豪放磊落な人物であり、その反骨精神とホットなライディングでGPをわかせる存在だった。 |
|
 |
 |
 |
| マシンも、まさに好対照だった。Hondaが1963年度のレースに投入したマシンは、並列4気筒DOHC4バルブというハイメカニズムを誇るRC164。一方モリーニは、原型を1958年に辿ることが出来る単気筒DOHCバルブスプリング剥き出しの古典的な構成。RC164が10,000rpm以上でウォーミングアップを行い、Hondaミュージックと言われる高回転のかん高いマルチサウンドを響かせるのに対し、モリーニは2,000rpmで野太いアイドリングをするという老兵だ。 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
しかしこの年、最終戦を前にして勝利数でレッドマン/Hondaを上回るプロビーニ/モリーニは、決してあなどれる存在ではなかった。公称48ps/14,500rpmと言われるRC164に対し、モリーニは41ps/11,000rpm。しかし車重に関してはRC164がそのエンジンゆえ130kgであるのに対し、モリーニはわずか105kgという軽量を誇る。つまりパワー/ウェイトレシオではRC164が2.71kg/psであるのに比べ、モリーニは2.33kg/psという有利な数値を実現していたのだ。 |
|
 |
| しかしレースは、そのプロビーニ/モリーニを置き去りにしたかたちで進んだ。日本へ渡航する機内で中耳炎を悪化させたプロビーニは完全に体調を崩し、その走りに本来の冴えは見られなかった。予選トップはレッドマンの2分31秒9。これにヤマハのフィル・リード、伊藤史朗が続き、プロビーニは7番手に沈み込んでいた。決勝レースでも、このフォーメーションに変化はなかった。レッドマンと、これを追うリード、伊藤の3人が好レースを展開し、プロビーニはスズキ2台のリタイヤに助けられて4位に入賞するのが精一杯だった。その結果レッドマンは2ポイントを加算し、この最終戦日本グランプリでタイトルを決定した。 |
 |
 |
|
 |
| それは、自ら世界GPに挑み、短期間で頂点にまで駆け昇り、そして日本初の本格的レーシングコースまでをも完成させたHondaにとって、記念すべき勝利とタイトル決定の瞬間でもあった。 |
 |
|
 |
 |
 |
その後、時代は徐々に変容していった。50、125ccクラスでは、スズキとヤマハの2ストロークマシンがその性能にさらなる磨きをかけ、その後の覇権を握ることになる。また250ccクラスでも、鈴鹿で大活躍を見せたフィル・リードとヤマハが台頭し、64、65年と連続してタイトルを手中にしている。350ccクラスではレッドマンと、その後のエースライダーとなったマイク・ヘイルウッドが、HondaがGPから撤退する67年まで、その牙城を守り抜いた。 |
|
 |
| 1963年、2ポイント差でタイトルを逃したプロビーニは、この年限りで老兵モリーニを降りる決心をした。これに代わってモリーニのシートを得たのが、若き日のジャコモ・アゴスチーニだった。アゴスチーニは翌64年、モリーニでGPデビューを果たし、彼にとって初のグランプリポイントを獲得し、その後に続く栄光のレース人生をスタートさせている。そしてMVワークスに迎え入れられた1965年、アゴスチーニは鈴鹿を訪れ、日本GPでの唯一のレースを経験している。 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
鈴鹿における日本GPは1963〜1965年まで開催され、66〜67年は富士スピードウェイ(FISCO)に所を移したが、日本メーカーのGPからの撤退と同調するように日本GPはその使命を終え、以後1987年まで日本でグランプリが開催されることはなかった。その1987年は、鈴鹿でF1が開催された記念すべき年でもあった。 |
|
 |
|
1964年、Hondaは4輪のF1へとチャレンジの場を拡大していた。65年にF1で初優勝を経験し、66年には新型3リッターマシンがデビュー。ヨーロッパではブラバムHondaが破竹の勢いでF2の連勝記録を伸ばしていた。その1966年、鈴鹿サーキットは4輪のレース統括団体であるFIAの国際トラックライセンスを取得していた。
Hondaの夢は、2輪での勝利を積み重ねながら、さらに大きく広がっていた。本田宗一郎のマン島TT出場宣言には、以下のように記されていた。
「私の幼き頃よりの夢は、自分で製作した自動車で全世界の自動車競争の覇者となることであつた。(中略)わが本田技研はこの難事業を是非とも完遂しなければならない。
日本の機械工業の真価を問い、これを全世界に誇示するまでにしなければならない。わが本田技研の使命は日本産業の啓蒙にある」
|