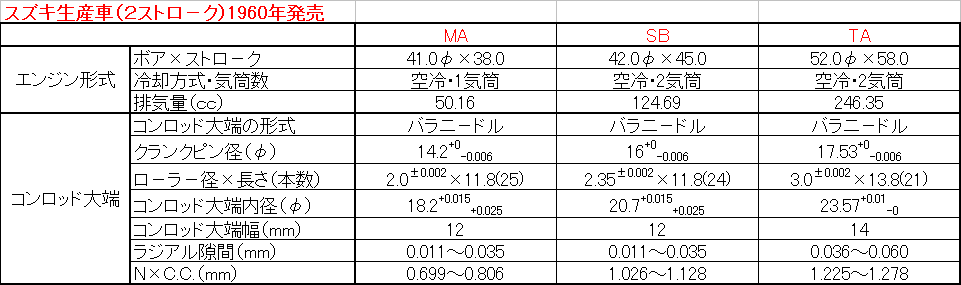
[第4表]
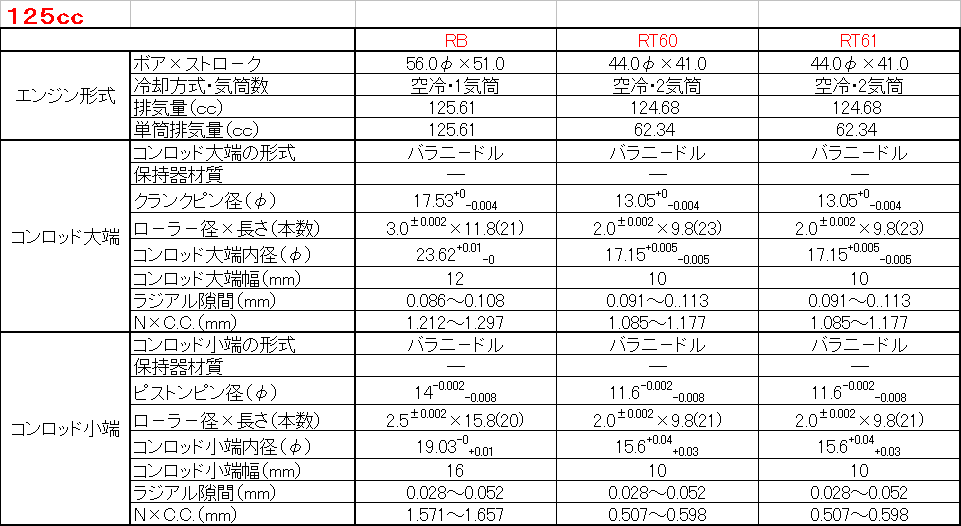
[第3表]
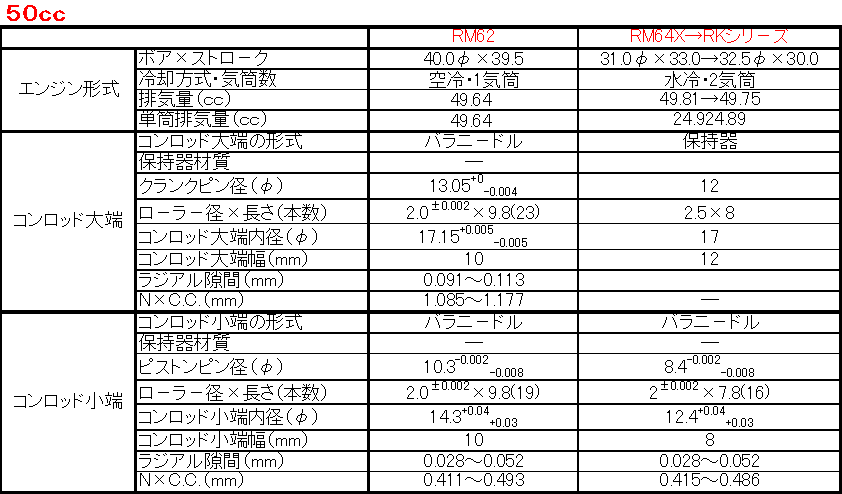
[第2表]
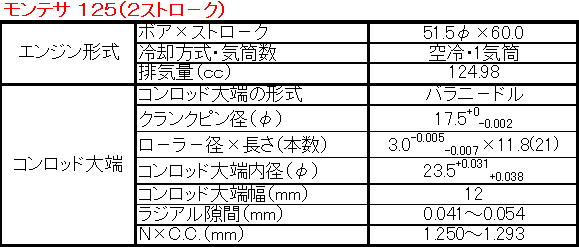
[第1表]
[コンロッド大小端へのバラニ-ドル方式の採用]
1959年の「第3回浅間火山レ-ス」の項で、参考車として購入したスペインの「モンテサ 125」を分解したところ、コンロッド大端に保持器を使用せず、ニ-ドルロ-ラ-を並べた方式であった(この方式は「バラニ-ドル方式」と名付けた)。当時、コンロッド大端の耐久性で悩まされていた「RBエンジン」に、この方式を採用することにより、高回転でも耐久性が得られたこと、また小端部にもこの方式を採用したことを述べた。
[第1表]には、スケッチした「モンテサ 125」の寸法を示す。特徴は「ラジアル隙間」が0.041~0.054と大きいこと、又、「N×C.C.」も1.250~1.293と大きいことである。「N×C.C.」とは、クランクピン上に、ロ-ラ-を密着させて並べた時の周方向隙間のことである。
[第2表]には、50ccワ-クスマシン、 [第3表]には、125ccワ-クスマシンを示す。50ccのコンロッド大端にはRM62にのみ「バラニ-ドル方式」を採用し、RM63以降は保持器付きを採用した。小端部にはRM62からRK67までのマシン全てにこの方式を採用した。125ccのコンロッド大端には「第3回浅間火山レ-ス」出場のRB、GPレ-ス出場のRT60・RT61に採用し、RT62以降は保持器付きを採用した。小端部にはRBからRS67までのマシン全てにこの方式を採用した。
なお、1960年発売の市販車MA型(50cc)、SB型(125ccTwin)、TA型(250ccTwin)のコンロッド大端には「バラニ-ドル方式」を採用した。これらを[第4表]に示す。
コンロッド大端に「バラニ-ドル方式」を採用するに当たっては、いろんなテストを実施したが、耐久性向上のためには、「クランクピン径」は強度の許す限り小さくすること、「ラジアル隙間」は 0.1前後と大きくとること、「N×C.C.」は 1mm位とることが必要とされた。1962年マン島初優勝のRM62は「バラニ-ドル方式」を採用していたが、その後の性能向上に伴い、細いクランクピン(13.05φ)の折損事故が発生し始め、RM63からは保持器付きに変更された。また、「ラジアル隙間」は 0.1前後と大きくとる必要があるため、打音の発生があり、レ-ス用マシンはともかく、市販車への採用は難しい面があった。なお、コンロッド小端部への採用に当たっては、大端部のような シビア-な面はなかった。
1959年の「第3回浅間火山レ-ス」の項で、参考車として購入したスペインの「モンテサ 125」を分解したところ、コンロッド大端に保持器を使用せず、ニ-ドルロ-ラ-を並べた方式であった(この方式は「バラニ-ドル方式」と名付けた)。当時、コンロッド大端の耐久性で悩まされていた「RBエンジン」に、この方式を採用することにより、高回転でも耐久性が得られたこと、また小端部にもこの方式を採用したことを述べた。
[第1表]には、スケッチした「モンテサ 125」の寸法を示す。特徴は「ラジアル隙間」が0.041~0.054と大きいこと、又、「N×C.C.」も1.250~1.293と大きいことである。「N×C.C.」とは、クランクピン上に、ロ-ラ-を密着させて並べた時の周方向隙間のことである。
[第2表]には、50ccワ-クスマシン、 [第3表]には、125ccワ-クスマシンを示す。50ccのコンロッド大端にはRM62にのみ「バラニ-ドル方式」を採用し、RM63以降は保持器付きを採用した。小端部にはRM62からRK67までのマシン全てにこの方式を採用した。125ccのコンロッド大端には「第3回浅間火山レ-ス」出場のRB、GPレ-ス出場のRT60・RT61に採用し、RT62以降は保持器付きを採用した。小端部にはRBからRS67までのマシン全てにこの方式を採用した。
なお、1960年発売の市販車MA型(50cc)、SB型(125ccTwin)、TA型(250ccTwin)のコンロッド大端には「バラニ-ドル方式」を採用した。これらを[第4表]に示す。
コンロッド大端に「バラニ-ドル方式」を採用するに当たっては、いろんなテストを実施したが、耐久性向上のためには、「クランクピン径」は強度の許す限り小さくすること、「ラジアル隙間」は 0.1前後と大きくとること、「N×C.C.」は 1mm位とることが必要とされた。1962年マン島初優勝のRM62は「バラニ-ドル方式」を採用していたが、その後の性能向上に伴い、細いクランクピン(13.05φ)の折損事故が発生し始め、RM63からは保持器付きに変更された。また、「ラジアル隙間」は 0.1前後と大きくとる必要があるため、打音の発生があり、レ-ス用マシンはともかく、市販車への採用は難しい面があった。なお、コンロッド小端部への採用に当たっては、大端部のような シビア-な面はなかった。