e
本文は、1970年(昭和45年)発行の『スズキ50年史』掲載されている記事である。私は1967年からレ−ス部門を離れていたが、社史編纂に当たり「レ−ス活動」についての執筆を命じられ、1959年(昭和34年)の第3回浅間火山レ−ス以降について原稿を書きました。
スズキの富士登山レースから1960年代のレース活動
レースへの参加と技術の向上
(1) 富士登山レースに連続優勝(昭和28〜29年)
昭和28年(1953)7月12日、第1回富士登山レースが毎日新聞社の主催で行われた。スズキは、その年3月発売の後、たちまち世間の人気を集めたダイヤモンド・フリー号(2サイクル60cc)をもってこれに参加し、優勝を勝ち取った。
富士登山レース以前のレースは、今でいうダートトラック・レースのようなもので、レーサーといっても、市販車を改造してただグラウンドを走りやすいように手を入れた程度のものを造り、浜松周辺では専売局跡や、磐田の城山などのグラウンドで走ることが多かった。それがしだいに熱があがってきて、レースで技術を競い合うことになり、富士登山レースということになった。


第2回浜松オートレース(東小学校)にダイヤモンドフリーも出場 富士登山レース
富士登山レース出場車も市販車をベースにしたものであったが、エンジン関係にはかなり手を入れたものであった。
このレースのバイク部門に、山下林作選手がダイヤモンド・フリー号に乗って優勝し、スズキの名声を高めたわけであるが、ダイヤモンド・フリー号はそれまでにすで市販されていて好評を得、非常な売れ行きであった。これに自信を得た技術陣は続いて、翌29年(1954)春、4サイクル90ccの完成車コレダ号CO型を完成、その年の第2回富士登山レース(日刊自動車新聞社主催)に再び山下選手がこのCO型で参加し、41分32秒8と、第2位を6.2秒引き離して連続優勝しスズキ技術の声価を確固たるものとしたのである。
(2)第1回浅間高原レース(昭和30年)
昭和30年(1955)になって、浅間山麓でレースを催す気運が高まり、日本小型自動車工業会の主催で第1回全日本オートバイ耐久ロードレース(通称第1回浅間高原レース)が11月5〜6両日に開かれることになった。
その開催要綱が決まると、スズキでは早速レーサーの設計に取りかかった。そのころスズキの市販車にはダイヤモンド・フリー号、ミニフリー号、コレダCO型があり、コレダST型(2サイクル125cc)の生産車を仕上げた直後であったが、これらとは全く別の角度から新しいレーサーを造ることになった
。
丸山設計課長以下のスタッフが設計を担当することになり、日曜日も返上しての努力の末、わずか40日で設計試作を終わった。出来上がったレーサーSV型は、市販車と異なって1本パイプのフレームで、後輪はスイングアーム式を採用したが、当時としては議論の的となった。エンジンはボアー52mm、ストローク58mmで、ST型と同じであったが、シリンダーのポートタイミング、空気通路には新しいアイデアを取り入れ、ミッションは市販車より1段増やして4段とした。
そのころ性能向上対策として、吸気関係には関心が寄せられていたが、肝心の排気関係には無関心で、メガホン型のマフラーを試作したものであった。出力は最終的に7馬力くらい出るようになった。
北軽井沢から1kmほど北にあった百楽荘にキャンプを置いて、レースまでに2回ばかり合宿練習を行った。
コースは上り下りの多い火山岩、火山灰でできた公道で行われ、1周19.2km、125ccクラスは4周であった。出場車はスズキ、ヤマハ、ホンダの他、ライラック、ミシマ、パール、昌和など計27台がスタートについた。

スタート風景
スズキは5名のライダーが出場。山下林作、鈴木英夫、神谷敏夫が完走して、それぞれ5位、6位、7位に入り、市野三千雄が17位、伊藤利一は転倒したが、結局スズキ、ヤマハ、ホンダの実力は極めて接近していると見られた。
このレースの結果はその後の業界の動向に大きな影響を与えた。浅間の溶岩コースで苦闘したライダーと、そのレーシング・マシンを造り上げた人たちとの力は、やがて世界一のオートバイを育て上げる力となったのである。
(3)第3回浅間火山レース(昭和34年)
第1回浅間レースの後で、スズキはレースに今後出場しない旨の声明を発表した。一方、浅間高原には、小型自動車工業会の手でテストコースの建設が進められ、昭和32年(1957)7月19日完成した。1周9.351km、火山灰をグレーダーでならしローラーで固めて、わが国では初めての本格的テストコースであった。観客収容の施設などはなかったが、ともかく本格的サーキットとして、充分レース使用に耐えるものであった。
この年10月、このコースで行われた最初の浅間火山レース(昭和30年のレースと通算して第2回)には、スズキは出場を見送ったが、昭和33年(1958)になると、やはりレースには参加すべきだとの意見が強まり、同年秋になり、翌昭和34年(1959)の第3回浅間火山レースで125ccクラスに出場する方針が決まり、それを目標に諸般の準備を始めた。
出場レーサーは「RB型」といい、空冷2サイクル単気筒、ボアー56mm、ストローク51mm、変速機段数は4段、最高出力は10PS/9000rpmであった。
スズキチームはレースの3カ月前、5月23日に本社を出発し、北軽井沢の地蔵川旅館に合宿して練習を行った。
エンジン性能にはかなりの自信があったが、コンロッド大端部の耐久性、ピストン頂頭の溶け、ピストンリングの折損など問題があり、その対策には非常な苦心を要した。特にコンロッド大端は、フルスロットルで走ると、わずか数kmで焼付くという状態で銀メッキのコンロッドやボールベアリングを使ってみたり、CCIまがいのコンロッド大端強制給油の実験もしてみたりしたが、思うにまかせず、一方、レース期日はいやおうなく近づいてくるので、すいぶん頭を悩ましたものであった。6月の半ば頃になって、当てずっぽうに近いやり方で4種類のクランクを合宿に持ち込み、テストをしたところ、保持器なしのバラニードル型式のものが、いくら走っても焼付かないことがわかって、やっと安心したことは、今でも生々しい記憶として残っている。このバラニードル型式は、従来の2サイクル・エンジンの壁を破った高回転エンジンMA型、SB型に採用されたものである。
当時のベンチ・テストは、狭い動力計室で行われ、エンジンのそばで耳栓をして出力測定を行ったものである。換気が悪いため、出力測定途中に煙で目盛板が見えなくなり、目が痛くなって中途で飛び出したこともしばしばであった。また、マフラーの形状を変えることで、出力が大幅に変わること(排気管の脈動効果)を知ったのも、その当時のことであった。
コンロッド大端のトラブルが解消されて、マシンの安定性が増し、ライダーもコースに慣れてくるにつれて、ラップタイムはしだいに向上した。第2回浅間火山レースでの最高ラップタイム6分16秒を大幅に破り、5分39秒5まで出せるようになった。
8月に入ると、ホンダの本命レーサーも姿を見せた。ホンダはその年の6月のマン島TTレースに日本メーカーとして初出場し、6、7、8、11位入賞の好成績を収めて帰国したばかりであった。しかし、練習タイムでは全く互角で、スズキの優勝も不可能ではないとの自信が持てた。
いよいよレース当日の8月23日になった。125ccクラスは、9.351kmのコースを14周である。メーカー出場車は、スズキが伊藤利一、市野三千雄、伊藤光夫、松本聡男、松本俊吉(旧姓増田)の5名、ホンダはツインTTレーサー4台、トーハツは2気筒4台、クルーザーが5台である。
1周目は、ホンダ谷口(TTレース6位)、伊藤光夫、ホンダ、スズキ伊藤利一、ホンダ、スズキ松本、スズキ市野の順位で、大勢は互角であった。スズキの増田はトップ・グループにありながら、惜しくも転倒して落伍した。2周目、伊藤光夫は1位に躍り出たが、転倒してしまった。5周目には1位だったホンダ谷口が転倒落伍した。順位は、ホンダ、スズキ伊藤利一、ホンダ、ホンダ、スズキ市野、スズキ松本となった。7周目に伊藤利一がガソリンタンク亀裂で落伍し、松本も最後の14周目にチェーン切れで落伍した。結果は、市野が5位に入賞しただけでホンダの圧勝ということになり、勝利の女神の祝福を受けることができなかったスズキのレース担当者は、皆、意気消沈して浅間を下った。
当時のレース・グループの陣容は次のとおりであった。( )は現職。
研究課長 岡野武治(研究部)
係長 清水正尚(第一設計部)
中野広之(特機設計第二課)
神谷安則(研究第一課)
稲垣久雄(研究第一課)
田口義郎(研究第一課)
鈴木清一(二輪エンジン課)
整備応援 袴田 勇(試作課)
鈴木三男(試作課)
関 光雄(サービス課)
増田正雄(36年退職)
伊藤義雄(工機課)
小林武男(工機課)
(4)マン島TTレースに初出場(昭和35年)
昭和34年(1959)、第3回浅間レースに破れた担当者一同は、「再びレースをやることはあるまい」という重い気持ちを抱いて浅間山を下ったのであったが、その年の暮れも押し詰まった頃、舞台は思わぬ方向に展開された。
出張旅行中の社長は、たまたま車中の本田技研工業の本田宗一郎社長と一緒になった。そのとき本田社長から「おたくのレーサーはえらくよく走るが、TTレースに出したらどうか」との話が持ち出された。こんなことがきっかけになって、翌年(1960)のTTレースに出場することが12月27日の企画会議で正式に決定された。
「また、レースがやれるんだ。しかも世界の檜舞台TTレースだ」ということでレース担当者は、正月休みも返上して新レーサーの図面書きに専念した。型式はRT60型、回転馬力を稼ぐために2気筒とし、初めての乾式クラッチ、6段ミッションを採用したが、参考資料も何もない。独自の設計のうえ、ぶっつけ本番の一発勝負という冒険で、製作完了前にすでにTTレース初参加が発表されており、全く背水の陣を敷いた形であった。
当時、走行テストをしたくともコースはなく、早朝に汐見坂東の国道1号線まで行ってレーサーテストをしたこともあった。しかし、もちろん国道で充分なテストができるはずがなかった。そのうち本田技研工業の荒川テストコースを借りてテストが行えるようになり、最高速度計測用のカウンターを借りたり、昼食を運んでもらったり、折れた部品を技術研究所で溶接してもらったり、ずいぶんお世話になったものである。レーサーや部品の送り方とか通関方法などについても教えを受けた。その後35年(1960)3月23日米津浜のテストコースが完成して、本格的にテストができるようになったのである。

米津浜テストコースが完成、テストを見る重役陣
これより先、2月1日丸山研究部長は、TTレース・コースの視察、宿舎の選定などのため渡英し、マン島コース60.725kmを全コースにわたって映画フィルムに収めて持ち帰った。
一方レーサーの方は、出力こそ当時としては一応満足できるものであったが、ピストン焼付き、頭部の溶けに悩まされ、近づく発送日を前にして頭を痛めることが多かった。やっとアルミニューム・シリンダーを採用することによって、ピストン・トラブルは解消され、5月9日、全社員参加の壮行会の後、本社を出発した。
そのときのチーム編成は、次のとおりでった。
監督 岡 野 武 治
チーフ 清 水 正 尚
設計員 中 野 広 之
整備員 神 谷 安 則
ライダー 伊 藤 光 夫
〃 市 野 三千雄
〃 松 本 聡 男
渉外 松 宮 昭
TTレースの行われるマン島は、イングランドとアイルランドの間のアイリッシュ海に浮かぶ小さな美しい島で、コースは1周60.725km、標高差は400m以上あって、非常にむずかしく、かつ立派なコースであり、従ってライダーに最高のレーシング・テクニックを、技術者には最高のメカニズムを要求する。このTTレースは世界各地の旅行者(Tourist)の間に行われるレースとして明治40年(1907年)から開催され、TTレース(Tourist Trophy Race)の名もそれに由来するが、世界の十数カ国で催される世界選手権レースの中で最も古く、最も権威があり、かつ最も困難なコースとされて、「TTレースを制するものは世界を制する」とさえいわれている。このレースに参加することは、単なるスポーツ的興味だけに留まるものではなく、オートバイ・メーカーの技術の真価が問われることを意味するのである。
なお、日本人で初めてTTレースに参加したのは、昭和5年(1930)に多田健蔵氏がイギリス製のベロセット車に乗って出場し、350ccクラスで15位になったときと言われる。
宿舎には、ダグラス湾を見下ろす丘の中腹にあるファンレイ・ホテルが充てられた。ここは東ドイツのMZチームも泊まっていた。MZは、当時2サイクルながら、スピードでは世界一を誇り、ライダーには、その後37年(1962)からスズキチームに加わって50ccクラスの世界選手権をもたらしたデグナーもいた。
TTレース・コースは公道であるため、普段はレーサーで走ることはできない。そのため練習車として送ったSBB150ccで練習した。
岡野監督はファンレイ・ホテルの主人ピアー氏に「何しにきたのか」と聞かれて、「レースに参加して勝つために来た」と答えると、「とんでもない。それじゃ教えてやろう」といって、次のようなお説教をされた。「1年目はコースを勉強せよ。2年目は初年度に勉強したことを織り込んで復習する年だ。3年目こそ勝たなきゃいかん」この言葉には、その後になって、なるほどと感心させられたものである。
いよいよ公式練習が始まった。公道であるため朝4時45分から6時30分まで、夕6時30分から8時まで交通を遮断して行われる。マン島は北緯54度に位置し、夏の昼間は長いのである。ところで、第1回目の公式練習の第1周目にアクシデントが起こった。伊藤光夫が山手のバンガロー地点で転倒、負傷したのである。同宿のMZのデグナー選手も、伊藤の事故の直前に、同じ地点で転倒し二人枕を並べて入院してしまった。このため伊藤の代わりに急遽R.フェイ選手を出場させることになった。
スズキの出場する125ccレースは、6月13日、コース3周182.175kmで行われたが、常勝イタリアのMV、東独のMZとの性能の差はいかんともしがたく松本15位、市野16位、フェイ18位に終わった。しかし、この難コースで、初出場ながら全車完走し、松本がブロンズ・レプリカ賞を受賞できたことは、まずまずの成果であった。
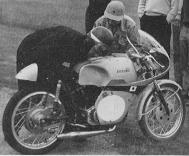

RT60 125cc レーサー 松本聡男が獲得したブロンズ・レプリカ
(5)苦闘の国際レース(昭和36年)
TTレース初出場の成果に気をよくした一同は、来年こそ上位入賞との覚悟を新たにして帰国すると、早速36年度(1961)の準備に取りかかった。


米津浜テストコースでのテスト風景 レーサー運搬用の車両
出場種目は、125ccに加えて250ccクラスにも出場することにし、TTレースの他に全GPレース出場を目標とすることになった。レーサーは、125cc、250ccともに2気筒ロータリーバルブ型式のものが新しく開発された。出場ライダーも、経験豊かな外人選手を起用することにし、P.ドライバー選手に着目した。ドライバーは3月上旬、夫人同伴で来日し、米津浜コースで試乗を行い、契約を結んだ。
いよいよ世界選手権レースの開幕となって、TT以前のスペイン、西ドイツ、フランスのレースには、P.ドライバーが125cc、250ccのレーサーをもって単独出場したが、成績は芳しくなかった。TTレースからは岡野総監督以下の選手団が送り込まれたが、トラブルに悩まされ、悪戦苦闘の連続であった。エンジン性能は前年度に較べて大分向上しており、満足に完走できれば昨年以上の成績を収め得たはずであるが、何分新機構を多く取り入れ過ぎたための、トラブルに悩まされることが多かったのである。
後の世界チャンピオン、アンダーソンがスズキチームに加わったのは、この年のTTレースからで、このとき彼は250ccで10位に入りブロンズ・レプリカ賞を受賞したが、続くオランダのレースでは、公式練習で転倒負傷し、入院治療のやむなきに至った。この入院が縁で、当時看護婦をしていたジャニー夫人と結ばれるというエピソードが生まれた。ベルギーのレースからは、アンダーソンに代わってペリスがスズキチームに加わった。
このレースには俊三社長も応援に駆けつけた。整備員として参加していた袴田勇は、オランダのレースを回想して、「背広を着たままの社長と二人で、車の中でエンジンの載せ替えをやったことは、いまだに忘れられない」と語っている。
TTレース、オランダ、ベルギーと、選手団の苦闘は続いたが、トラブルは解消されなかった。結局、全レース出場の予定は取り止めて、重い足を引きずりながら帰国することになった。
この年から、125cc、250ccクラスで常勝のMVが引退し、代わってホンダが両クラスの選手権を獲得した。ヤマハも、フランス、TTレース、オランダ、ベルギーに、初めて選手団を送り込んだが、成績ははかばかしくなかった。
その2へ Menu へ
スズキの富士登山レースから1960年代のレース活動
レースへの参加と技術の向上
(1) 富士登山レースに連続優勝(昭和28〜29年)
昭和28年(1953)7月12日、第1回富士登山レースが毎日新聞社の主催で行われた。スズキは、その年3月発売の後、たちまち世間の人気を集めたダイヤモンド・フリー号(2サイクル60cc)をもってこれに参加し、優勝を勝ち取った。
富士登山レース以前のレースは、今でいうダートトラック・レースのようなもので、レーサーといっても、市販車を改造してただグラウンドを走りやすいように手を入れた程度のものを造り、浜松周辺では専売局跡や、磐田の城山などのグラウンドで走ることが多かった。それがしだいに熱があがってきて、レースで技術を競い合うことになり、富士登山レースということになった。


第2回浜松オートレース(東小学校)にダイヤモンドフリーも出場 富士登山レース
富士登山レース出場車も市販車をベースにしたものであったが、エンジン関係にはかなり手を入れたものであった。
このレースのバイク部門に、山下林作選手がダイヤモンド・フリー号に乗って優勝し、スズキの名声を高めたわけであるが、ダイヤモンド・フリー号はそれまでにすで市販されていて好評を得、非常な売れ行きであった。これに自信を得た技術陣は続いて、翌29年(1954)春、4サイクル90ccの完成車コレダ号CO型を完成、その年の第2回富士登山レース(日刊自動車新聞社主催)に再び山下選手がこのCO型で参加し、41分32秒8と、第2位を6.2秒引き離して連続優勝しスズキ技術の声価を確固たるものとしたのである。
(2)第1回浅間高原レース(昭和30年)
昭和30年(1955)になって、浅間山麓でレースを催す気運が高まり、日本小型自動車工業会の主催で第1回全日本オートバイ耐久ロードレース(通称第1回浅間高原レース)が11月5〜6両日に開かれることになった。
その開催要綱が決まると、スズキでは早速レーサーの設計に取りかかった。そのころスズキの市販車にはダイヤモンド・フリー号、ミニフリー号、コレダCO型があり、コレダST型(2サイクル125cc)の生産車を仕上げた直後であったが、これらとは全く別の角度から新しいレーサーを造ることになった
。
丸山設計課長以下のスタッフが設計を担当することになり、日曜日も返上しての努力の末、わずか40日で設計試作を終わった。出来上がったレーサーSV型は、市販車と異なって1本パイプのフレームで、後輪はスイングアーム式を採用したが、当時としては議論の的となった。エンジンはボアー52mm、ストローク58mmで、ST型と同じであったが、シリンダーのポートタイミング、空気通路には新しいアイデアを取り入れ、ミッションは市販車より1段増やして4段とした。
そのころ性能向上対策として、吸気関係には関心が寄せられていたが、肝心の排気関係には無関心で、メガホン型のマフラーを試作したものであった。出力は最終的に7馬力くらい出るようになった。
北軽井沢から1kmほど北にあった百楽荘にキャンプを置いて、レースまでに2回ばかり合宿練習を行った。
コースは上り下りの多い火山岩、火山灰でできた公道で行われ、1周19.2km、125ccクラスは4周であった。出場車はスズキ、ヤマハ、ホンダの他、ライラック、ミシマ、パール、昌和など計27台がスタートについた。

スタート風景
スズキは5名のライダーが出場。山下林作、鈴木英夫、神谷敏夫が完走して、それぞれ5位、6位、7位に入り、市野三千雄が17位、伊藤利一は転倒したが、結局スズキ、ヤマハ、ホンダの実力は極めて接近していると見られた。
このレースの結果はその後の業界の動向に大きな影響を与えた。浅間の溶岩コースで苦闘したライダーと、そのレーシング・マシンを造り上げた人たちとの力は、やがて世界一のオートバイを育て上げる力となったのである。
(3)第3回浅間火山レース(昭和34年)
第1回浅間レースの後で、スズキはレースに今後出場しない旨の声明を発表した。一方、浅間高原には、小型自動車工業会の手でテストコースの建設が進められ、昭和32年(1957)7月19日完成した。1周9.351km、火山灰をグレーダーでならしローラーで固めて、わが国では初めての本格的テストコースであった。観客収容の施設などはなかったが、ともかく本格的サーキットとして、充分レース使用に耐えるものであった。
この年10月、このコースで行われた最初の浅間火山レース(昭和30年のレースと通算して第2回)には、スズキは出場を見送ったが、昭和33年(1958)になると、やはりレースには参加すべきだとの意見が強まり、同年秋になり、翌昭和34年(1959)の第3回浅間火山レースで125ccクラスに出場する方針が決まり、それを目標に諸般の準備を始めた。
出場レーサーは「RB型」といい、空冷2サイクル単気筒、ボアー56mm、ストローク51mm、変速機段数は4段、最高出力は10PS/9000rpmであった。
スズキチームはレースの3カ月前、5月23日に本社を出発し、北軽井沢の地蔵川旅館に合宿して練習を行った。
エンジン性能にはかなりの自信があったが、コンロッド大端部の耐久性、ピストン頂頭の溶け、ピストンリングの折損など問題があり、その対策には非常な苦心を要した。特にコンロッド大端は、フルスロットルで走ると、わずか数kmで焼付くという状態で銀メッキのコンロッドやボールベアリングを使ってみたり、CCIまがいのコンロッド大端強制給油の実験もしてみたりしたが、思うにまかせず、一方、レース期日はいやおうなく近づいてくるので、すいぶん頭を悩ましたものであった。6月の半ば頃になって、当てずっぽうに近いやり方で4種類のクランクを合宿に持ち込み、テストをしたところ、保持器なしのバラニードル型式のものが、いくら走っても焼付かないことがわかって、やっと安心したことは、今でも生々しい記憶として残っている。このバラニードル型式は、従来の2サイクル・エンジンの壁を破った高回転エンジンMA型、SB型に採用されたものである。
当時のベンチ・テストは、狭い動力計室で行われ、エンジンのそばで耳栓をして出力測定を行ったものである。換気が悪いため、出力測定途中に煙で目盛板が見えなくなり、目が痛くなって中途で飛び出したこともしばしばであった。また、マフラーの形状を変えることで、出力が大幅に変わること(排気管の脈動効果)を知ったのも、その当時のことであった。
コンロッド大端のトラブルが解消されて、マシンの安定性が増し、ライダーもコースに慣れてくるにつれて、ラップタイムはしだいに向上した。第2回浅間火山レースでの最高ラップタイム6分16秒を大幅に破り、5分39秒5まで出せるようになった。
8月に入ると、ホンダの本命レーサーも姿を見せた。ホンダはその年の6月のマン島TTレースに日本メーカーとして初出場し、6、7、8、11位入賞の好成績を収めて帰国したばかりであった。しかし、練習タイムでは全く互角で、スズキの優勝も不可能ではないとの自信が持てた。
いよいよレース当日の8月23日になった。125ccクラスは、9.351kmのコースを14周である。メーカー出場車は、スズキが伊藤利一、市野三千雄、伊藤光夫、松本聡男、松本俊吉(旧姓増田)の5名、ホンダはツインTTレーサー4台、トーハツは2気筒4台、クルーザーが5台である。
1周目は、ホンダ谷口(TTレース6位)、伊藤光夫、ホンダ、スズキ伊藤利一、ホンダ、スズキ松本、スズキ市野の順位で、大勢は互角であった。スズキの増田はトップ・グループにありながら、惜しくも転倒して落伍した。2周目、伊藤光夫は1位に躍り出たが、転倒してしまった。5周目には1位だったホンダ谷口が転倒落伍した。順位は、ホンダ、スズキ伊藤利一、ホンダ、ホンダ、スズキ市野、スズキ松本となった。7周目に伊藤利一がガソリンタンク亀裂で落伍し、松本も最後の14周目にチェーン切れで落伍した。結果は、市野が5位に入賞しただけでホンダの圧勝ということになり、勝利の女神の祝福を受けることができなかったスズキのレース担当者は、皆、意気消沈して浅間を下った。
当時のレース・グループの陣容は次のとおりであった。( )は現職。
研究課長 岡野武治(研究部)
係長 清水正尚(第一設計部)
中野広之(特機設計第二課)
神谷安則(研究第一課)
稲垣久雄(研究第一課)
田口義郎(研究第一課)
鈴木清一(二輪エンジン課)
整備応援 袴田 勇(試作課)
鈴木三男(試作課)
関 光雄(サービス課)
増田正雄(36年退職)
伊藤義雄(工機課)
小林武男(工機課)
(4)マン島TTレースに初出場(昭和35年)
昭和34年(1959)、第3回浅間レースに破れた担当者一同は、「再びレースをやることはあるまい」という重い気持ちを抱いて浅間山を下ったのであったが、その年の暮れも押し詰まった頃、舞台は思わぬ方向に展開された。
出張旅行中の社長は、たまたま車中の本田技研工業の本田宗一郎社長と一緒になった。そのとき本田社長から「おたくのレーサーはえらくよく走るが、TTレースに出したらどうか」との話が持ち出された。こんなことがきっかけになって、翌年(1960)のTTレースに出場することが12月27日の企画会議で正式に決定された。
「また、レースがやれるんだ。しかも世界の檜舞台TTレースだ」ということでレース担当者は、正月休みも返上して新レーサーの図面書きに専念した。型式はRT60型、回転馬力を稼ぐために2気筒とし、初めての乾式クラッチ、6段ミッションを採用したが、参考資料も何もない。独自の設計のうえ、ぶっつけ本番の一発勝負という冒険で、製作完了前にすでにTTレース初参加が発表されており、全く背水の陣を敷いた形であった。
当時、走行テストをしたくともコースはなく、早朝に汐見坂東の国道1号線まで行ってレーサーテストをしたこともあった。しかし、もちろん国道で充分なテストができるはずがなかった。そのうち本田技研工業の荒川テストコースを借りてテストが行えるようになり、最高速度計測用のカウンターを借りたり、昼食を運んでもらったり、折れた部品を技術研究所で溶接してもらったり、ずいぶんお世話になったものである。レーサーや部品の送り方とか通関方法などについても教えを受けた。その後35年(1960)3月23日米津浜のテストコースが完成して、本格的にテストができるようになったのである。

米津浜テストコースが完成、テストを見る重役陣
これより先、2月1日丸山研究部長は、TTレース・コースの視察、宿舎の選定などのため渡英し、マン島コース60.725kmを全コースにわたって映画フィルムに収めて持ち帰った。
一方レーサーの方は、出力こそ当時としては一応満足できるものであったが、ピストン焼付き、頭部の溶けに悩まされ、近づく発送日を前にして頭を痛めることが多かった。やっとアルミニューム・シリンダーを採用することによって、ピストン・トラブルは解消され、5月9日、全社員参加の壮行会の後、本社を出発した。
そのときのチーム編成は、次のとおりでった。
監督 岡 野 武 治
チーフ 清 水 正 尚
設計員 中 野 広 之
整備員 神 谷 安 則
ライダー 伊 藤 光 夫
〃 市 野 三千雄
〃 松 本 聡 男
渉外 松 宮 昭
TTレースの行われるマン島は、イングランドとアイルランドの間のアイリッシュ海に浮かぶ小さな美しい島で、コースは1周60.725km、標高差は400m以上あって、非常にむずかしく、かつ立派なコースであり、従ってライダーに最高のレーシング・テクニックを、技術者には最高のメカニズムを要求する。このTTレースは世界各地の旅行者(Tourist)の間に行われるレースとして明治40年(1907年)から開催され、TTレース(Tourist Trophy Race)の名もそれに由来するが、世界の十数カ国で催される世界選手権レースの中で最も古く、最も権威があり、かつ最も困難なコースとされて、「TTレースを制するものは世界を制する」とさえいわれている。このレースに参加することは、単なるスポーツ的興味だけに留まるものではなく、オートバイ・メーカーの技術の真価が問われることを意味するのである。
なお、日本人で初めてTTレースに参加したのは、昭和5年(1930)に多田健蔵氏がイギリス製のベロセット車に乗って出場し、350ccクラスで15位になったときと言われる。
宿舎には、ダグラス湾を見下ろす丘の中腹にあるファンレイ・ホテルが充てられた。ここは東ドイツのMZチームも泊まっていた。MZは、当時2サイクルながら、スピードでは世界一を誇り、ライダーには、その後37年(1962)からスズキチームに加わって50ccクラスの世界選手権をもたらしたデグナーもいた。
TTレース・コースは公道であるため、普段はレーサーで走ることはできない。そのため練習車として送ったSBB150ccで練習した。
岡野監督はファンレイ・ホテルの主人ピアー氏に「何しにきたのか」と聞かれて、「レースに参加して勝つために来た」と答えると、「とんでもない。それじゃ教えてやろう」といって、次のようなお説教をされた。「1年目はコースを勉強せよ。2年目は初年度に勉強したことを織り込んで復習する年だ。3年目こそ勝たなきゃいかん」この言葉には、その後になって、なるほどと感心させられたものである。
いよいよ公式練習が始まった。公道であるため朝4時45分から6時30分まで、夕6時30分から8時まで交通を遮断して行われる。マン島は北緯54度に位置し、夏の昼間は長いのである。ところで、第1回目の公式練習の第1周目にアクシデントが起こった。伊藤光夫が山手のバンガロー地点で転倒、負傷したのである。同宿のMZのデグナー選手も、伊藤の事故の直前に、同じ地点で転倒し二人枕を並べて入院してしまった。このため伊藤の代わりに急遽R.フェイ選手を出場させることになった。
スズキの出場する125ccレースは、6月13日、コース3周182.175kmで行われたが、常勝イタリアのMV、東独のMZとの性能の差はいかんともしがたく松本15位、市野16位、フェイ18位に終わった。しかし、この難コースで、初出場ながら全車完走し、松本がブロンズ・レプリカ賞を受賞できたことは、まずまずの成果であった。
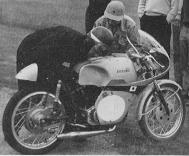

RT60 125cc レーサー 松本聡男が獲得したブロンズ・レプリカ
(5)苦闘の国際レース(昭和36年)
TTレース初出場の成果に気をよくした一同は、来年こそ上位入賞との覚悟を新たにして帰国すると、早速36年度(1961)の準備に取りかかった。


米津浜テストコースでのテスト風景 レーサー運搬用の車両
出場種目は、125ccに加えて250ccクラスにも出場することにし、TTレースの他に全GPレース出場を目標とすることになった。レーサーは、125cc、250ccともに2気筒ロータリーバルブ型式のものが新しく開発された。出場ライダーも、経験豊かな外人選手を起用することにし、P.ドライバー選手に着目した。ドライバーは3月上旬、夫人同伴で来日し、米津浜コースで試乗を行い、契約を結んだ。
いよいよ世界選手権レースの開幕となって、TT以前のスペイン、西ドイツ、フランスのレースには、P.ドライバーが125cc、250ccのレーサーをもって単独出場したが、成績は芳しくなかった。TTレースからは岡野総監督以下の選手団が送り込まれたが、トラブルに悩まされ、悪戦苦闘の連続であった。エンジン性能は前年度に較べて大分向上しており、満足に完走できれば昨年以上の成績を収め得たはずであるが、何分新機構を多く取り入れ過ぎたための、トラブルに悩まされることが多かったのである。
後の世界チャンピオン、アンダーソンがスズキチームに加わったのは、この年のTTレースからで、このとき彼は250ccで10位に入りブロンズ・レプリカ賞を受賞したが、続くオランダのレースでは、公式練習で転倒負傷し、入院治療のやむなきに至った。この入院が縁で、当時看護婦をしていたジャニー夫人と結ばれるというエピソードが生まれた。ベルギーのレースからは、アンダーソンに代わってペリスがスズキチームに加わった。
このレースには俊三社長も応援に駆けつけた。整備員として参加していた袴田勇は、オランダのレースを回想して、「背広を着たままの社長と二人で、車の中でエンジンの載せ替えをやったことは、いまだに忘れられない」と語っている。
TTレース、オランダ、ベルギーと、選手団の苦闘は続いたが、トラブルは解消されなかった。結局、全レース出場の予定は取り止めて、重い足を引きずりながら帰国することになった。
この年から、125cc、250ccクラスで常勝のMVが引退し、代わってホンダが両クラスの選手権を獲得した。ヤマハも、フランス、TTレース、オランダ、ベルギーに、初めて選手団を送り込んだが、成績ははかばかしくなかった。
その2へ Menu へ