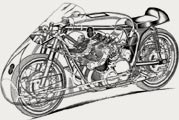、昭和39年の日本…というか東京の中心部には、明らかに戦後最大のイベント開催に向けてある種の高揚した雰囲気が漂っていた。都心には首都高速道路という、鉄腕アトムの未来都市の様な(そんな大袈裟なモンじゃなかったけれど…)道路が造られ、東京の一般道には一気に信号と横断歩道が増えた。原宿の木造オンボロ長屋に住んでいた鼻垂れ小僧のボクは、家の前の明治通りに植え込みが出来て街が綺麗になっていくのを子供心に感じていた。日曜になるとやって来るロバのパン屋さんが五輪パンと言うのを売っていたし、2階の物干しに登ると北東の方向に巨大な建造物が出来つつあるのが見えた。親父に聞くと「日本もロケットを打ち上げる秘密基地を造ってるんだ」という嘘をつかれ、ボクはそれを半分以上は信じていた。実はそれが国立競技場であり、それを核とする東京オリンピックが、当時の日本人の最大の関心事だった。 、昭和39年の日本…というか東京の中心部には、明らかに戦後最大のイベント開催に向けてある種の高揚した雰囲気が漂っていた。都心には首都高速道路という、鉄腕アトムの未来都市の様な(そんな大袈裟なモンじゃなかったけれど…)道路が造られ、東京の一般道には一気に信号と横断歩道が増えた。原宿の木造オンボロ長屋に住んでいた鼻垂れ小僧のボクは、家の前の明治通りに植え込みが出来て街が綺麗になっていくのを子供心に感じていた。日曜になるとやって来るロバのパン屋さんが五輪パンと言うのを売っていたし、2階の物干しに登ると北東の方向に巨大な建造物が出来つつあるのが見えた。親父に聞くと「日本もロケットを打ち上げる秘密基地を造ってるんだ」という嘘をつかれ、ボクはそれを半分以上は信じていた。実はそれが国立競技場であり、それを核とする東京オリンピックが、当時の日本人の最大の関心事だった。 |
 |
 まさにそんな1964年の夏、Hondaの朝霞研究所では驚くべき秘密兵器の開発が進められていた。この年、グランプリの250ccクラスでヤマハの高性能2ストロークマシンに苦しめられ、シーズン2勝しかあげることの出来ないHondaは、ついに6気筒マシンという起死回生の秘密兵器を準備していたのだ。8月8日の第9戦アルスターGP終了後急遽帰国した秋鹿監督が新型マシンの仕上がりを確認。ジム・レッドマンは8月30日第10戦フィンランドGPを終えるとそのまま来日し、このマシンをテスト。その時点で250cc6気筒の実戦配備が決定され、9月13日の第11戦イタリアGPに間に合わせるべく空輸の準備が進められた。東京オリンピックの開会式10月10日まで1ヶ月を切って日本中が三波春男の東京五輪音頭に浮かれている頃、Honda内部では6気筒プロジェクトが緊迫した最終段階を迎えていた。 まさにそんな1964年の夏、Hondaの朝霞研究所では驚くべき秘密兵器の開発が進められていた。この年、グランプリの250ccクラスでヤマハの高性能2ストロークマシンに苦しめられ、シーズン2勝しかあげることの出来ないHondaは、ついに6気筒マシンという起死回生の秘密兵器を準備していたのだ。8月8日の第9戦アルスターGP終了後急遽帰国した秋鹿監督が新型マシンの仕上がりを確認。ジム・レッドマンは8月30日第10戦フィンランドGPを終えるとそのまま来日し、このマシンをテスト。その時点で250cc6気筒の実戦配備が決定され、9月13日の第11戦イタリアGPに間に合わせるべく空輸の準備が進められた。東京オリンピックの開会式10月10日まで1ヶ月を切って日本中が三波春男の東京五輪音頭に浮かれている頃、Honda内部では6気筒プロジェクトが緊迫した最終段階を迎えていた。 |
 |
 |
 |
厳しい日程の都合で、レッドマンは鈴鹿でのテストを行えず、荒川の直線往復路でこのマシンを走らせただけでOKサインを出したというのだから、いかにスケジュールが押し迫っていたかが想像出来ようというものだ。レッドマンが離日し、マシンがすでに空輸されてからも鈴鹿でのテストは続けられ、最終データが蓄積されていた。 |
|
| |
|
GPのレースウィークになってやっとイタリアに到着した新型マシンは、しかし空港の通関で難癖をつけられてなかなか出てこられなかった。この件に興味を持っていたボクは、後年になってイタリア人のジャーナリストに尋ねたことがある。すると答えはこうだった。
「イタリアGPのあるモンツァに入るには、ミラノの空港からだろ?。あそこは正式にはMilan-Malpensa空港って言うんだ。MV
Agsutaの社名はMeccanica Verghera Agustaの略で、VergheraはMalpensaの近くの地名なんだ。つまりミラノ空港はMV
Agsutaのお膝元にあるわけ。MVは航空産業でも有名な企業だったから空港関係者にだって知り合いはいっぱいいるだろう。つまりMVの影の圧力でHondaのマシンが通関に足止めをくらったとしても、なんの不思議はない…ということだよ」
|
 |
| まさに謎が渦巻くスパイ小説のような話だが、ボクはMVのそれまでの手練手管から考えて、まったくの作り話ではない気がした。MVのレース界における権謀術数は、並大抵のモノではなかったのも事実だ。まして、自分のホームコースであるモンツァだ。日本からの新型マシンのエントリーを食い止めるためになんらかのチカラが働いたとしても、おかしくはない。ボクは、MVはすでに木枠の中のマシンが6気筒だと分かっていたのではないかとさえ考えた。「6気筒」…それはMVにとっても曰くつきのマシンだった。 |
 |
 |
|
 |
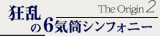 |
 |
 と「モンツァ」は、MVにとって因縁の組み合わせだった。1957年、500ccクラスで最強のライバルであるジレラとの対決用に6気筒のマシンを完成させたMVは、最終戦のモンツァに向けてこれを準備した。とは言うものの、実戦的な性能を発揮したと言うにはほど遠かったようで、実際のレースにそのマシンが姿を現すことはないまま、またそのマシンの存在が知られることもないまま、時間は過ぎていった。 と「モンツァ」は、MVにとって因縁の組み合わせだった。1957年、500ccクラスで最強のライバルであるジレラとの対決用に6気筒のマシンを完成させたMVは、最終戦のモンツァに向けてこれを準備した。とは言うものの、実戦的な性能を発揮したと言うにはほど遠かったようで、実際のレースにそのマシンが姿を現すことはないまま、またそのマシンの存在が知られることもないまま、時間は過ぎていった。 |
 |
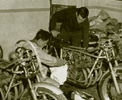 そして翌1958年の最終戦モンツァにも6気筒はサーキットに持ち込まれたが、ライダーのジョン・ハートルがリタイヤしたことで、6気筒は二度と衆目の前にその姿をさらすことはなくなってしまった。この1958年にはジレラがワークス活動を撤退しており、それ以上無理をして6気筒を投入する必要がなくなっていたのがその最大の理由だ。この年の最終戦モンツァでは、ジョン・サーティースらがMVで1-2-3を決め、実質的にはライバル不在の状態だった。ハートルによれば6気筒は恐ろしくパワーバンドが狭く、またすべての気筒がきちんと回ることもないという気むずかしいエンジンで、栄光のMVの歴史の中でも出来れば闇に葬りたい失敗作であったようだ。 そして翌1958年の最終戦モンツァにも6気筒はサーキットに持ち込まれたが、ライダーのジョン・ハートルがリタイヤしたことで、6気筒は二度と衆目の前にその姿をさらすことはなくなってしまった。この1958年にはジレラがワークス活動を撤退しており、それ以上無理をして6気筒を投入する必要がなくなっていたのがその最大の理由だ。この年の最終戦モンツァでは、ジョン・サーティースらがMVで1-2-3を決め、実質的にはライバル不在の状態だった。ハートルによれば6気筒は恐ろしくパワーバンドが狭く、またすべての気筒がきちんと回ることもないという気むずかしいエンジンで、栄光のMVの歴史の中でも出来れば闇に葬りたい失敗作であったようだ。 |
 |
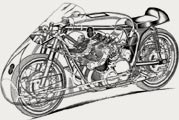 |
 |
グランプリにおけるマルチエンジンの歴史は、戦前にさかのぼることが出来る。ジレラの4気筒は1947年に世界選手権がスタートする前から大きな成功を収めており、MVの4気筒は、このジレラの開発者をそのまま引き抜いて同じ4気筒を作らせたものだった。だから、MVでは「コピーマシンで栄光を手にした」という風評を一掃しようと6気筒を開発したという面子の部分もあっただろうが、残念ながらそのマシンは最後までモノにならずお蔵入りとなってしまったのだ。 |
|
 |
| その直前には、モト・グッチがなんとV型8気筒の500ccマシンを投入したこともある。1956/1957年の2シーズンにわたって何戦かのGPを走ったV8だったが、これも実戦的な性能を発揮することなく、4位に3回入賞したのが最高の成績だった。MVの6気筒とグッチの8気筒は、ともに75馬力前後という当時としては圧倒的なパワーを発揮し、最高速でも他を大きく引き離していたようだが、マシンセットアップの困難さ、増大した重量による劣悪な操縦性、さらに解決しがたい程のオーバーヒートに悩まされ、とにかく主力機種とは成り得ずにその短い命を終えることとなった。 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
そんな、苦闘のマルチエンジンの歴史を持つイタリアの地に持ち込まれたHondaの6気筒がなんとか通関をくぐり抜け、モンツァのトラックに姿をあらわしたのは、レースの前日だった。Hondaにしてみれば、慌ただしい手続きを終えてなんとか本番に間に合った…という感じだったが、パドックの多くの人々にとっては、ギリギリまでその存在を隠した秘密兵器と受け取られたことだろう。 |
|
 |
 そして6気筒エンジンに火が入ると、それまで聞いたこともないカン高いエキゾーストノートにパドックの人々は凍りついた。まぎれもなく6本の口を開いたマフラー。しかしマシンのカウル幅は4気筒と変わらぬまでにコンパクトであり、本当にこれが6気筒であるのか信じられない人々がHondaのパドックを幾重にも囲んだ。しかし、コースインして行ったレッドマンのストレートスピードは、明らかに4気筒を凌ぐものだった。秋鹿監督は、完璧に調整されたエンジン音に満足げだった。4気筒でコースにいたルイジ・タベリはピットに戻るなり「自分は125に乗っていて250に抜かれるみたいだ」と、その驚愕の速さをチームスタッフに告げた。 そして6気筒エンジンに火が入ると、それまで聞いたこともないカン高いエキゾーストノートにパドックの人々は凍りついた。まぎれもなく6本の口を開いたマフラー。しかしマシンのカウル幅は4気筒と変わらぬまでにコンパクトであり、本当にこれが6気筒であるのか信じられない人々がHondaのパドックを幾重にも囲んだ。しかし、コースインして行ったレッドマンのストレートスピードは、明らかに4気筒を凌ぐものだった。秋鹿監督は、完璧に調整されたエンジン音に満足げだった。4気筒でコースにいたルイジ・タベリはピットに戻るなり「自分は125に乗っていて250に抜かれるみたいだ」と、その驚愕の速さをチームスタッフに告げた。
|
 |
| MVのピットも、そのスピードに目を見張るしかなかった。1959年のマン島TT初挑戦以来、MVの偉大な記録を次々に塗り替えてきたHondaが送り込んだ次なる新兵器は、彼らが実現を試みながら遂にその達成を諦めざるを得なかった6気筒マシンそのものであり、ましてそれはMVの500ccに対して半分の250ccで成し遂げられた目の前の現実だった。マン島TT初挑戦時に「時計のように精巧なエンジン」と称えられたHondaは、その6気筒のエキゾーストノートに「Hondaミュージック」という新たな称号を与えられた。 |
 |
 |
 |
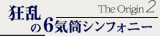 |
 |
 、やはり到着したばかりで実戦的なテストが皆無だった6気筒は、思わぬトラブルに見舞われた。3周目には2位以下に6秒の差をつけて快走していたレッドマンだったが、その後周回が進むにつれてエンジン音にばらつきが混じるようになった。ヤマハのフィル・リードはこの隙を逃さずトップに立ち、徐々に差を広げると彼にとって初めての年間タイトルを決定する記念すべきチェッカーフラッグを受けた。 、やはり到着したばかりで実戦的なテストが皆無だった6気筒は、思わぬトラブルに見舞われた。3周目には2位以下に6秒の差をつけて快走していたレッドマンだったが、その後周回が進むにつれてエンジン音にばらつきが混じるようになった。ヤマハのフィル・リードはこの隙を逃さずトップに立ち、徐々に差を広げると彼にとって初めての年間タイトルを決定する記念すべきチェッカーフラッグを受けた。 |
 |
 |
|
 |
| レッドマンの6気筒の不調は、エンジン本体のトラブルではなかった。それまでにない発熱量が燃料パイプを襲い、タンクからキャブまでの経路にベーパーロック…つまり気泡が発生し息つき現象をおこしていたのだった。口さがないイタリア人達は、やはり6気筒など無理だったのだと納得顔だったが、秋鹿監督以下Hondaチームの面々は、すべての面で6気筒が4気筒を凌ぐモノであることを確認し、大きな満足を得ていた。パワー、操縦性、あらゆる部分で新型6気筒はレースに革新をもたらしたと言ってもいいだろう。なにしろ4気筒の車重が125kg前後であったのに対し、6気筒はなんと115kgを実現していたのだ。 |
 |
 |
 |
そしてその証明は、11月1日の最終戦日本グランプリで達成されることになる。問題点をクリアした6気筒を駆るレッドマンは他を圧倒し、見事に優勝。それは世界グランプリ史上初めて6気筒のマシンがウィニングチェッカーを受ける瞬間だった。東京オリンピックの直前に6気筒マシンのデビューを実現したHondaチームは、そのオリンピック終了後1週間の時点でついに大きな栄光を勝ち取った。オリンピックという壮大なイベントの影で、歴史的なチャレンジが行われていたこともまた興味深い。オリンピック最終日の男子マラソンを甲州街道まで見に行ったボクは、当時6気筒マシンの優勝などつゆ知らず、円谷の力走に涙したものだった。 |
|
 |
| その後、Hondaは125ccの5気筒、350ccにも6気筒を投入。50ccでも2気筒が奮闘し、4ストロークDOHC4バルブの多気筒エンジンという高度な技術を完全に確立していくことになる。これには、MVも他のヨーロッパのメーカーも追従することは出来なかった。ライバルと成り得たのはヤマハとスズキの2ストローク勢だったが、こちらもまた多気筒化を進め、250cc4気筒、125cc4気筒、50cc2気筒、さらには50ccの3気筒までが計画されていた。 |
 |
 |
|
 |
| これらの攻勢に太刀打ち出来るメーカーは、他にはなかった。1960年代の世界グランプリは、完全に日本製マシンに席巻されていた。そして、その事実がまた、GPを変容させる大きな要因となったことは否めない。マシンレギュレーションは、限られた勢力の独占を許さないように抑制を加える機能を持つ。戦前にBMWが圧倒的な過給技術でグランプリを制覇したことで、1949年からの世界選手権はスーパーチャージャーの装着を禁止した。1950年代にイタリア車が前輪までもすっぽりと覆う大型のダストビンカウルを装着して最高速を飛躍的に向上した時も、横風の影響を受けて危険との理由でこれが禁止された。 |
 |
 |
 |
1969年シーズンから、世界グランプリに出場出来るマシンは、500/350ccクラスが4気筒まで。250/125ccクラスが2気筒まで、50ccクラスが単気筒という制限が加えられることとなった。また、ミッション段数の上限も設けられ、厳しい騒音規制も付け加えられた。これは明らかに、高度に発達した…または発達し過ぎてしまった日本製マシンをグランプリから閉め出すための方策だった。 |
|
 |
| 歴史的に見れば、1960年代の世界グランプリはある種の異様な進化を遂げてしまった時代なのかもしれない。戦前には、速度記録という目標を目指してBMWが航空機から過給技術を取り入れ、またこれに対抗すべくジレラなどは4気筒というマルチエンジンを開発して一気にマシンの高度化を進めた。60年代の日本メーカーによるGP制覇は、それらを遙かに凌ぐものだったのは確かだ。Hondaミュージックと称されたマルチエンジンの咆哮はまた、ライバル達を完全に駆逐してしまうほど力強過ぎる雄叫びであったのかもしれない。 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
時は流れ、東京オリンピックから40年近くを経て、来年にはサッカーのワールドカップが開催されようとしている。そして、オリンピックと肩を並べるこの世界的なスポーツイベント開催のシーズン、世界グランプリはまた大きなマシンレギュレーションの変更を受けようとしている。Hondaも5気筒の500ccマシンRC211Vの熟成を進めていることだろう。新時代を迎える4ストロークマルチのHondaミュージックは、21世紀にどんなサウンドを奏でるのだろうか。そして21世紀のロードレースは、どのように推移していくのだろうか。 |
|
 |
| 今ボクの住んでいる近所の歩道橋の上から、真南の方向に横浜国際総合競技場が見える。ワールドカップの決勝がそこで開催される来年6月の最終週、RC211Vはすでに第7戦アッセンでのグランプリを迎えているはずだ。大きな大きな時の流れが、日本や、レースや、テクノロジーや、そして自分の何を変え、また何を変えていないのか、40年近くの時を隔てて、ボクはじっくり感じ取ろうと思っている。 |


 まさにそんな1964年の夏、Hondaの朝霞研究所では驚くべき秘密兵器の開発が進められていた。この年、グランプリの250ccクラスでヤマハの高性能2ストロークマシンに苦しめられ、シーズン2勝しかあげることの出来ないHondaは、ついに6気筒マシンという起死回生の秘密兵器を準備していたのだ。8月8日の第9戦アルスターGP終了後急遽帰国した秋鹿監督が新型マシンの仕上がりを確認。ジム・レッドマンは8月30日第10戦フィンランドGPを終えるとそのまま来日し、このマシンをテスト。その時点で250cc6気筒の実戦配備が決定され、9月13日の第11戦イタリアGPに間に合わせるべく空輸の準備が進められた。東京オリンピックの開会式10月10日まで1ヶ月を切って日本中が三波春男の東京五輪音頭に浮かれている頃、Honda内部では6気筒プロジェクトが緊迫した最終段階を迎えていた。
まさにそんな1964年の夏、Hondaの朝霞研究所では驚くべき秘密兵器の開発が進められていた。この年、グランプリの250ccクラスでヤマハの高性能2ストロークマシンに苦しめられ、シーズン2勝しかあげることの出来ないHondaは、ついに6気筒マシンという起死回生の秘密兵器を準備していたのだ。8月8日の第9戦アルスターGP終了後急遽帰国した秋鹿監督が新型マシンの仕上がりを確認。ジム・レッドマンは8月30日第10戦フィンランドGPを終えるとそのまま来日し、このマシンをテスト。その時点で250cc6気筒の実戦配備が決定され、9月13日の第11戦イタリアGPに間に合わせるべく空輸の準備が進められた。東京オリンピックの開会式10月10日まで1ヶ月を切って日本中が三波春男の東京五輪音頭に浮かれている頃、Honda内部では6気筒プロジェクトが緊迫した最終段階を迎えていた。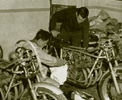 そして翌1958年の最終戦モンツァにも6気筒はサーキットに持ち込まれたが、ライダーのジョン・ハートルがリタイヤしたことで、6気筒は二度と衆目の前にその姿をさらすことはなくなってしまった。この1958年にはジレラがワークス活動を撤退しており、それ以上無理をして6気筒を投入する必要がなくなっていたのがその最大の理由だ。この年の最終戦モンツァでは、ジョン・サーティースらがMVで1-2-3を決め、実質的にはライバル不在の状態だった。ハートルによれば6気筒は恐ろしくパワーバンドが狭く、またすべての気筒がきちんと回ることもないという気むずかしいエンジンで、栄光のMVの歴史の中でも出来れば闇に葬りたい失敗作であったようだ。
そして翌1958年の最終戦モンツァにも6気筒はサーキットに持ち込まれたが、ライダーのジョン・ハートルがリタイヤしたことで、6気筒は二度と衆目の前にその姿をさらすことはなくなってしまった。この1958年にはジレラがワークス活動を撤退しており、それ以上無理をして6気筒を投入する必要がなくなっていたのがその最大の理由だ。この年の最終戦モンツァでは、ジョン・サーティースらがMVで1-2-3を決め、実質的にはライバル不在の状態だった。ハートルによれば6気筒は恐ろしくパワーバンドが狭く、またすべての気筒がきちんと回ることもないという気むずかしいエンジンで、栄光のMVの歴史の中でも出来れば闇に葬りたい失敗作であったようだ。 そして6気筒エンジンに火が入ると、それまで聞いたこともないカン高いエキゾーストノートにパドックの人々は凍りついた。まぎれもなく6本の口を開いたマフラー。しかしマシンのカウル幅は4気筒と変わらぬまでにコンパクトであり、本当にこれが6気筒であるのか信じられない人々がHondaのパドックを幾重にも囲んだ。しかし、コースインして行ったレッドマンのストレートスピードは、明らかに4気筒を凌ぐものだった。秋鹿監督は、完璧に調整されたエンジン音に満足げだった。4気筒でコースにいたルイジ・タベリはピットに戻るなり「自分は125に乗っていて250に抜かれるみたいだ」と、その驚愕の速さをチームスタッフに告げた。
そして6気筒エンジンに火が入ると、それまで聞いたこともないカン高いエキゾーストノートにパドックの人々は凍りついた。まぎれもなく6本の口を開いたマフラー。しかしマシンのカウル幅は4気筒と変わらぬまでにコンパクトであり、本当にこれが6気筒であるのか信じられない人々がHondaのパドックを幾重にも囲んだ。しかし、コースインして行ったレッドマンのストレートスピードは、明らかに4気筒を凌ぐものだった。秋鹿監督は、完璧に調整されたエンジン音に満足げだった。4気筒でコースにいたルイジ・タベリはピットに戻るなり「自分は125に乗っていて250に抜かれるみたいだ」と、その驚愕の速さをチームスタッフに告げた。