e
鈴木誠一さん(セイちゃん)の思い出
日本で「最初(第1回)の全日本モトクロス大会」が開催されたのは、1959年4月、大阪府下信太山だった。城北ライダースは、開催者の酒井文人氏に出場を要請され、主将の鈴木誠一と松内弘之(当時芝浦工大生)の二人で出かけ、クラブ優勝して、優勝旗を箱根を越して持ち帰った。
翌1960年春の「第2回全日本モトクロス(朝霧)」では、予想に反して荒井、桂田、池田、吉田の兵庫レーシングにクラブ優勝をさらわれたが、秋の「第3回全日本モトクロス」では、鈴木誠一、久保寿夫、和夫の兄弟、森下勲、松内弘之という強力メンバーの城北ライダースがクラブ優勝をとりもどした。これより城北ライダースの連覇が始まるのである。
このような城北ライダースとスズキに深い繋がりが出来たのは、東京支店の営業部門の尽力で、1961年の初めの頃だったと思う。我々レース担当部門との初顔合わせは、WGP参加準備でテンヤワンヤしていた3月24日だった。弁天島の保養所「コレダ荘」で、城北ライダースとスズキレース部門との親睦会を開催した。城北ライダースからどのようなメンバーが出席したのだったかは、記憶にないが・・・。
スズキ車に乗り換えての初レース、5月7日の朝霧での「第4回全日本モトクロス」に城北ライダースは、圧倒的な強さでクラブ優勝2連覇を達成した(この連覇の記録は7連覇までは知っているが、どこまで続いたのかは知らない)。スズキからは、市販車、部品を提供していただけで、マシン作りは全て城北ライダースがやっており、アマチュア集団(失礼!)を率いる鈴木誠一さんのチューニング技術に感心したものだった。その後、5月26日に鈴木誠一氏が来社、続いて6月1日には鈴木誠一・久保和夫両氏が来社して、チューニングについて、いろいろ意見交換をしたりもした。その後も、彼らとは数多くの打合せを持ったものだった。
続いて、7月21~23日には埼玉県武蔵町のジョンソン基地で「第4回 全日本クラブマンレース」が開催された。鈴木誠一さんというとこのレースが印象深く、真っ先に思い浮かぶ。この年、スズキはヨーロッパでのWGPに、125ccのRT61、250ccのRV61で挑戦していたが、いづれも故障だらけで完走もおぼつかない状況にあり、全WGP出場予定だった計画を取りやめ、スケジュール半ばのベルギーGPをもって帰国することになったような状態だった。《メニュー(1)表の【1961年本文】を参照》こんな状況下にも拘わらず営業部門より、RT61、RV61での本クラブマンレースへの強い出場要請があり、強引に押し切られたような状態で、やむを得ず出場することになった。本クラブマンレースには、「日本選手権レ-ス」というカテゴリがあり、ライダー・マシンの出場制限はなく、そして「クラブマンレース」での上位入賞者5名が招待されるというレースだった。ライダーは両マシンともに「城北ライダース」の鈴木誠一さんと久保和夫さんで出場することになった。WGPで完走出来ないマシンが、完走出来る筈はない・・・なんとか完走してくれと祈りながら、ジョンソン基地にマシンを持ち込んだ。125ccレースは、レース序盤は4,5位というところで久保さんは早くもリタイア。鈴木誠一さんは徐々に追い上げ何とか優勝。250ccレースは、鈴木誠一さんだけが出場。スタートは150mくらい押しても始動しない。見かねた競技役員らがマシンを押し(ここで失格)やっと始動してスタートして行った。トップとはもう2キロ半以上遅れていた。その後徐々に追い上げ、レース中盤には、何とか2位にまで追い上げたが、失格を知ってリタイアしたが、観衆は鈴木誠一さんの追い込みに大喜びだった。125cc、250ccともに、鈴木誠一さんの大奮闘で何とか面目を保つことが出来た、脳裏に残る忘れられないレースである。
1962年、鈴木誠一さんには、4月22・23日開催の「シンガポールGP」に、ワークスマシンのRT62(125cc)、RV62(250cc)で出場し、そして、そのままヨーロッパに向い、ヨーロッパでは、新しくWGPに加わった50ccに新開発のRM62で参戦することになった。しかし、鈴木誠一さんは、「シンガポールGP」250ccレースで惜しくもスリップ転倒し足を負傷してしまった。スズキのヨーロッパWGP選手団(筆者もその一員)は4月25日羽田を出発し、翌26日パリー空港でシンガポールからの鈴木誠一さんたちと合流した。日本からの私たちの便が先に到着し1時間半ほど待って、シンガポールからの便が到着し、彼が杖をついて出てきたのを今も鮮明に覚えている。ヨーロッパでの第1戦スペインGPは足の怪我が癒えず欠場、第2戦のフランスGPではスズキ最高位の5位、第3戦のTTレースでは8位(このレースでDegner が優勝しスズキにWGP初優勝をもたらした)、第4戦の Dutch TT と第5戦のベルギーGPでは共にスズキ日本人ライダーの中では最高位の4位、第6戦の西ドイツGPでは5位と大いに活躍した。このヨーロッパでの約3ヶ月間、私は鈴木誠一さんと起居、行動をともにした。なお、11月の鈴鹿の初レース「第1回全日本ロードレース選手権」にもRM62に乗り、ホンダの谷口尚巳さんと同タイムの4位の成績を残した。尚、鈴木誠一さん不在中に開催された4月28・29日の「第6回全日本モトクロス」を一手に引き受けた久保和夫さんが大活躍して、城北ライダースの連勝記録を4連覇とのばしたことも深く印象に残っている。
1965年から、スズキは「世界選手権ロードレ-ス(WGP)」に加え、「世界選手権モトクロスレ-ス」にも挑戦することになりました。1965年には久保和夫さんと鈴木誠一さん、1966年には久保和夫さんと小島松久さん、1967年には小島松久さんとWGPを引退したAndersonに出場して貰いました。日本人として、「世界選手権モトクロスレ-ス」に出場したのは城北ライダースの彼らが最初のことでした。
1967年をもってスズキは「世界選手権ロードレ-ス(WGP)」を撤退することになり、私は他の技術部門に移り、城北ライダースとのお付き合いはなくなりましたが、スズキレース部門との親しいお付き合いは続きました。
その後、鈴木誠一さんが四輪レースに転向され、大活躍なさっていたことは、勿論記憶に残っています。
1974年6月2日鈴木誠一さん事故死の訃報が入り、大きなショックを受けました。私の日誌には、このことが記載されています。当時、私は二輪の商品設計部門に在籍し、スズキ最初の4サイクル二輪車GSシリーズの開発を担当しており、葬儀の日に丁度或るメーカーとの打合せで出張になり、葬儀への出席は出来ず、浜松本社から列席する誰かにお香典を託した記憶があります。
事故発生の状況日本で「最初(第1回)の全日本モトクロス大会」が開催されたのは、1959年4月、大阪府下信太山だった。城北ライダースは、開催者の酒井文人氏に出場を要請され、主将の鈴木誠一と松内弘之(当時芝浦工大生)の二人で出かけ、クラブ優勝して、優勝旗を箱根を越して持ち帰った。
翌1960年春の「第2回全日本モトクロス(朝霧)」では、予想に反して荒井、桂田、池田、吉田の兵庫レーシングにクラブ優勝をさらわれたが、秋の「第3回全日本モトクロス」では、鈴木誠一、久保寿夫、和夫の兄弟、森下勲、松内弘之という強力メンバーの城北ライダースがクラブ優勝をとりもどした。これより城北ライダースの連覇が始まるのである。
このような城北ライダースとスズキに深い繋がりが出来たのは、東京支店の営業部門の尽力で、1961年の初めの頃だったと思う。我々レース担当部門との初顔合わせは、WGP参加準備でテンヤワンヤしていた3月24日だった。弁天島の保養所「コレダ荘」で、城北ライダースとスズキレース部門との親睦会を開催した。城北ライダースからどのようなメンバーが出席したのだったかは、記憶にないが・・・。
スズキ車に乗り換えての初レース、5月7日の朝霧での「第4回全日本モトクロス」に城北ライダースは、圧倒的な強さでクラブ優勝2連覇を達成した(この連覇の記録は7連覇までは知っているが、どこまで続いたのかは知らない)。スズキからは、市販車、部品を提供していただけで、マシン作りは全て城北ライダースがやっており、アマチュア集団(失礼!)を率いる鈴木誠一さんのチューニング技術に感心したものだった。その後、5月26日に鈴木誠一氏が来社、続いて6月1日には鈴木誠一・久保和夫両氏が来社して、チューニングについて、いろいろ意見交換をしたりもした。その後も、彼らとは数多くの打合せを持ったものだった。
続いて、7月21~23日には埼玉県武蔵町のジョンソン基地で「第4回 全日本クラブマンレース」が開催された。鈴木誠一さんというとこのレースが印象深く、真っ先に思い浮かぶ。この年、スズキはヨーロッパでのWGPに、125ccのRT61、250ccのRV61で挑戦していたが、いづれも故障だらけで完走もおぼつかない状況にあり、全WGP出場予定だった計画を取りやめ、スケジュール半ばのベルギーGPをもって帰国することになったような状態だった。《メニュー(1)表の【1961年本文】を参照》こんな状況下にも拘わらず営業部門より、RT61、RV61での本クラブマンレースへの強い出場要請があり、強引に押し切られたような状態で、やむを得ず出場することになった。本クラブマンレースには、「日本選手権レ-ス」というカテゴリがあり、ライダー・マシンの出場制限はなく、そして「クラブマンレース」での上位入賞者5名が招待されるというレースだった。ライダーは両マシンともに「城北ライダース」の鈴木誠一さんと久保和夫さんで出場することになった。WGPで完走出来ないマシンが、完走出来る筈はない・・・なんとか完走してくれと祈りながら、ジョンソン基地にマシンを持ち込んだ。125ccレースは、レース序盤は4,5位というところで久保さんは早くもリタイア。鈴木誠一さんは徐々に追い上げ何とか優勝。250ccレースは、鈴木誠一さんだけが出場。スタートは150mくらい押しても始動しない。見かねた競技役員らがマシンを押し(ここで失格)やっと始動してスタートして行った。トップとはもう2キロ半以上遅れていた。その後徐々に追い上げ、レース中盤には、何とか2位にまで追い上げたが、失格を知ってリタイアしたが、観衆は鈴木誠一さんの追い込みに大喜びだった。125cc、250ccともに、鈴木誠一さんの大奮闘で何とか面目を保つことが出来た、脳裏に残る忘れられないレースである。
1962年、鈴木誠一さんには、4月22・23日開催の「シンガポールGP」に、ワークスマシンのRT62(125cc)、RV62(250cc)で出場し、そして、そのままヨーロッパに向い、ヨーロッパでは、新しくWGPに加わった50ccに新開発のRM62で参戦することになった。しかし、鈴木誠一さんは、「シンガポールGP」250ccレースで惜しくもスリップ転倒し足を負傷してしまった。スズキのヨーロッパWGP選手団(筆者もその一員)は4月25日羽田を出発し、翌26日パリー空港でシンガポールからの鈴木誠一さんたちと合流した。日本からの私たちの便が先に到着し1時間半ほど待って、シンガポールからの便が到着し、彼が杖をついて出てきたのを今も鮮明に覚えている。ヨーロッパでの第1戦スペインGPは足の怪我が癒えず欠場、第2戦のフランスGPではスズキ最高位の5位、第3戦のTTレースでは8位(このレースでDegner が優勝しスズキにWGP初優勝をもたらした)、第4戦の Dutch TT と第5戦のベルギーGPでは共にスズキ日本人ライダーの中では最高位の4位、第6戦の西ドイツGPでは5位と大いに活躍した。このヨーロッパでの約3ヶ月間、私は鈴木誠一さんと起居、行動をともにした。なお、11月の鈴鹿の初レース「第1回全日本ロードレース選手権」にもRM62に乗り、ホンダの谷口尚巳さんと同タイムの4位の成績を残した。尚、鈴木誠一さん不在中に開催された4月28・29日の「第6回全日本モトクロス」を一手に引き受けた久保和夫さんが大活躍して、城北ライダースの連勝記録を4連覇とのばしたことも深く印象に残っている。
1965年から、スズキは「世界選手権ロードレ-ス(WGP)」に加え、「世界選手権モトクロスレ-ス」にも挑戦することになりました。1965年には久保和夫さんと鈴木誠一さん、1966年には久保和夫さんと小島松久さん、1967年には小島松久さんとWGPを引退したAndersonに出場して貰いました。日本人として、「世界選手権モトクロスレ-ス」に出場したのは城北ライダースの彼らが最初のことでした。
1967年をもってスズキは「世界選手権ロードレ-ス(WGP)」を撤退することになり、私は他の技術部門に移り、城北ライダースとのお付き合いはなくなりましたが、スズキレース部門との親しいお付き合いは続きました。
その後、鈴木誠一さんが四輪レースに転向され、大活躍なさっていたことは、勿論記憶に残っています。
1974年6月2日鈴木誠一さん事故死の訃報が入り、大きなショックを受けました。私の日誌には、このことが記載されています。当時、私は二輪の商品設計部門に在籍し、スズキ最初の4サイクル二輪車GSシリーズの開発を担当しており、葬儀の日に丁度或るメーカーとの打合せで出張になり、葬儀への出席は出来ず、浜松本社から列席する誰かにお香典を託した記憶があります。
「カーグラフィック誌」1974年8月号より引用
1974年6月2日の富士GC300キロレース第2ヒート(富士スピードウエイ)
それはすさまじいスタートだった。先頭は国光、その斜め後方に黒沢、その左に北野、3台のマーチ・BMWは、右後方に高原を従えて、バンクに向かって猛然と加速して行った。ヒートⅠで苦汁をなめさせらていた黒沢は”今度こそ”の意気に燃えていたし、北野とて絶対に譲れぬ勝負だった。言うまでもなく、バンクに突入するにはアウト側から行くのが理想的なコース、たがって、僅かにリードする国光の直後に2台並んだ北野と黒沢は、軽く接触しながら徐々にそのラインをアウト側に移して行った。そしてショートカット手前200-300mあたりまで来た時、北野はついに黒沢にハジキ出されるようにアウト側のグリーンに飛び出し、マシーンはそのロードホールディングの大半を失ってスピン、250km/h近くで疾走して来る後続マシーンの中をまっしぐらに横切っていった。白いマーチはまず米山のシェヴロンのノーズにぶち打たり、続いてショートカットへ逃げ込もうとしていた漆原のマーチともつれながら滑って行き、結局ショートカット入口で漆原のマシーンの下敷きになって止まった。漆原がまずコクピットから飛び出し、続いてほぼ同時に北野も漆原に助け出された直後、2台のマーチは火を吹きはじめた。だが、その左側ではもっと恐ろしいことが起こっていた。前方でのクラッシュを認めてとっさに左にステアリングを切ったのだろう、風戸のシェヴロンと鈴木のローラがガードレールをなぎ倒してグリーンに転がり、燃え盛っていたのだった。風戸は果敢にも自力でマシーンから脱出、ヘルメットを脱いで力つきたようにその場に倒れたという。一方の鈴木は、消火活動の終わるまでコクピットに閉じこめられていた。
消防車、および救急車がすぐさま出動、一方、国光をリーダーとして最終コーナーから現われた生き残りのマシーンには、”アクシデント発生、全車一時待機せよ”の意味を持つブラック・フラッグとチェッカーとが提示された。ペースを落としつつも2ラップ目に突入した彼らは、そのラップを終えてスタートライン上に止まった。”全員無事”との場内アナウンスが流れ、レース再開を期してコース上のマシーンたちがタイア交換を始めた直後、”最悪の事態のもよう”との第2報が伝わった。なんとも残念なことに、風戸裕、鈴木誠一の2人のドライバーが、全身のヤケドが原因で死亡してしまったのである。北野と漆原は軽いかすり傷のみで無事、米山も無事、接触の直後にいた高原も無事で、なかば放心状態で抱えられながらパドックへ帰って来た。一方、現場で撮影していたカメラマンが両脚骨折とヤケドで重傷、観客の4人も軽いヤケドを負った。
一瞬にして2人のドライバーを失うという日本のレース史上最大の悲しいアクシデントが発生してしまった。
鈴木誠一氏(セイさん)の追悼文:
「カーグラフィック誌」1974年8月号より引用
ひとは彼を「セイさん」と呼んだ。そして彼には、その呼び名が全くふさわしかった。37才。GCシリーズ出場ドライバー中の最年長者。大ベテランである。モーターサイクルから4輪に転向した彼のデビューレースは、1964年5月、鈴鹿サーキットで行われた第2回日本グランプリであった。大挙出場したワークス・ブルーバードSSを駆ってTーⅥレースにデビューした彼は、プラクティス、レースとも、田中健二郎に続いて2位になっている。その後の彼のドライバーとしての活躍は枚挙にいとまのないほどだが、彼の名を高めたのは、なんといってもNAC主催のストックカー・レースであった。NO.84を駆るセイさんは圧倒的な速さで連勝を続け、シリーズのウインナーに与えられるアメリカのデートナ・500マイルレースへの挑戦権を2度も授かっている。その間も日産チームの一員としてスカイラインGTR、フェアレディZなどで常に上位に食い込んでいたことはいうまでもない。
だが、彼を語る上で決して忘れてはならないのは、マシン・デベロッパーとしての類稀な才能であろう。ストックカーで彼に幾多の勝利を与えたセドリックは、無論彼のスピードショップ、東名自動車のチューンだったことは余りにも有名だ。さらに、現在1.3リッタークラスのTSレースを完全に制しているサニー1200を、メーカーよりも早くレーシングマシンに仕立て上げたのも、彼であった。70年11月、FISCOで行われたトランスニクス・レースにおいて、当時そのクラスで無敵を誇っていた4台の自販ワークス・カローラ、パブリカ勢にたった1台の東名サニーで挑戦した彼は見事愛車を1位に導き、それ以降のサニー全盛の火付け役となったのであった。
以後、東名サニーは圧倒的な速さと信頼性とを示し続け、それは今日でも変わらない。東名チューンのA12エンジンは、ワークスのそれよりもパワフルだ、というのが定説にさえなったほどだ。その原動力となった「セイさん」が、昨年からローラT292という2リッタースポーツの世界に乗り込みはじめた。そして最終戦において、ついに念願のGC初勝利を果たす。「ここまで来るのに1年かかりました」という彼の言葉は印象的だった。彼が次に夢見ていたものは、レーシングスポーツ用の16バルブ2リッターユニットの開発だったという。それを果たせずに往ってしまった「セイさん」のご冥福を、心からお祈りしたい。今年のGC第1戦のスタート前、リラックスした他のドライバーたちの中で、高橋健二の乗る東名サニーの戦いぶりをパドックのフェンス越しにひとり見守る彼の姿が忘れられない。
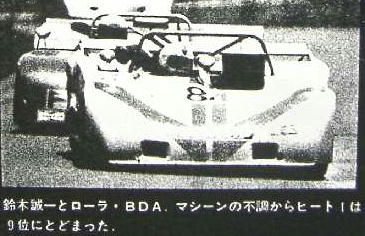

牧野弘文さんの【日本列島を駆け抜けたストックカー伝説】もご覧下さい
Menu へ